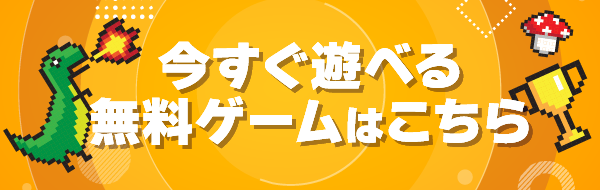キープコンセプトに思われる新型フィアット500。しかしそのデザインは、アンチ“現行モデル”の意志に満ちているとみることもできる。ここでは、そのデザインに何が起きているのか、カタチが見せるメッセージを読み解いてみたい。
EVとして2020年春に発表された新型フィアット500は、現行モデルに比較して全長が+60mmの3630mm、全幅が+60mmの1685mm、そして全高は同一の1515mm。やや長く、幅広くなったものの、充分にAセグメントに留まる。
現行モデルと比較してみると、かなり似た形をしていることはわかるが、そのディテールや全体のフォルムには、とある強い意志を感じ取ることができる。
そして同時に、この造形はおそらく現在のフィアット・ラインアップのなかでもっともエレガンスなものといっていいだろう。
事実上4代目となる新型フィアット500

……といいつつも、その前にこれまでのフィアット500のデザインから、その流れを見ていこう。
じつはEVとなった新型フィアット500は500という数字の名前でカウントすると4代目となる。このスタイルを周知させた2代目モデルはフィアット・ヌウォーヴァ500 (Nuova 500)と呼ばれていた。
それは先代があったためで、初代のフィアット500は1930年代に誕生している。


FRレイアウトの2シーターで、当時できるだけ安価に提供できる国民車として登場した。とはいうものの、写真を見てもわかるようにキャンバスルーフを備え、スタイリッシュなボディを持つ。
つまりは、決して我慢の車ではなく、移動すること、走ることを楽しむためのモデルでもあった。
その小ささから、ハツカネズミを意味するイタリア語“トポリーノ”の愛称で親しまれ大きな人気を得た。しかしその後、4シーターのルノー4CVやシトロエン2CVが登場し、利便性の観点からトポリーノの人気は衰退していった。
当初は2代目はフィアット600だったが、より小型化し人気拡大

そしてトポリーノの後継となったのが、1955年に登場したフィアット600だった。トポリーノ同等の全長で4人が乗れるモデルとしており、その実現のためにRRレイアウトが採用された。
そしてその2年後に600と同様のレイアウトをとりながら、ひとまわり小さいサイズで登場したのが500だ。
あえて名前にヌウォーヴァと付けていたように、フィアットとしても路線変更をし、むしろこちらがトポリーノの後継と捉え直したようだ。


2代目のヌウォーヴァ500はまさに最小限の必然性から生まれたデザインで、その形を見ると製造過程も想像できてしまうような合理性に富んでいる。ラインや分割されたパーツの造形は、シンプルなプレスでしっかりとした剛性のあるパネルとすることが考えられている。その結果生まれた造形が、パワフルな面の張りを感じさせ可愛らしさに通じるようだ。さらに先代のトポリーノにも見られるが、サッシまで一体としたドアパネルは、極めて合理的でコストや軽量化を重視。シェル状として左右に大きく開くフロントフードも、トランクエリアの利便性を高めると同時に剛性も高める構造となっている。
さらに、フロントフードのオープニングラインは、ボディをぐるりと一周するキャラクターラインとしている。このラインによって上下を分けることで、小さな車でありながらも、どっしりと安定感のある下半身を表現。さらに前後ともにフェンダーフレアが強調される造形ができているのは、上から見たときに前後を絞り込んだ樽型の造形になっていることも貢献している。
1950年代半ばのモデルながら、そのデザインセンスは極めて洗練されている。
異端となったモデルも…
 |  |
この後、500という名前は1975年に消滅し、1972年より500のユニットを利用して誕生した126というRRモデルが後継と見なされた。そのスタイルは500のオマージュも感じられるモデルとなったが、その後、1980年に初代パンダ、1991年に500の意味のイタリア語であるCinquecento (チンクエチェント)という名前を持ったFFレイアウトの新型車を発表。これらのモデルについても興味深い話題は多いのだが、生い立ちの経緯もやや異なることから今回は純粋に“500”という名前のあるモデルで世代を数えて話を進めたい。
ちなみにフィアットとしては、500の第1世代を最初のRRレイアウトモデル=ヌウォーヴァ (1957年誕生)、第2世代をFF化された現行モデル (2007年誕生)、第3世代を今回のEVモデル (2020年誕生)と捉えている。
必要最小限で必要にして十分…そしてファン さらに…

ここまででわかることは、「いかに小さく、必要充分な車とすることができるか」が500のコンセプトの中心にあることだ。そこには、シトロエン2CVやルノー4CVや、その後に登場したルノー4などを大きく凌駕する利便性とコンパクトさを追求し続ける姿勢を見ることができる。
じつにコンパクトでありながら、必要最小限のユーティリティ。そして、初代フィアット500トポリーノから貫かれた、ファンな存在。その実現こそがフィアット500が持ち続ける価値だ。
その意志を象徴するかのように、2代目のRRからFF、そしてEVへと変わってきた500だが、その形は誰が見ても変わらないものとなっている。しかし、ここには常に、フィアット・デザインの巧みな努力が見えてくる。
さらに庶民とエレガントを結びつける、イタリアらしさの開花させた。その辺りのデザインの考え方については、デザイン考2で見ていきたいと思う。