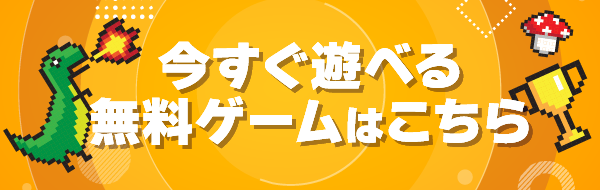「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」の違いについて、見た目や食感などが異なるのは経験的にわかるけれど、作り方や栄養価なども違うのかと聞かれると、実際には意外と知らない方が多いかもしれません。知っていたら選び方が少し変わるかもしれない!?豆腐の豆知識をご紹介します。
木綿豆腐と絹ごし豆腐は作り方が異なる
見た目や食感の異なる木綿豆腐と絹ごし豆腐ですが、その違いは作り方にあります。
よく知られている通り、豆腐の原材料は大豆。豆腐は豆乳を大豆から搾り取り、それを固めて作っていきます。
少し詳しく説明すると、まず水に浸した大豆を細かく砕き、「呉(ご)」と呼ばれる大豆の汁をとります。この呉を加熱して、「豆乳」と「おから」に分離させ、豆乳からさまざまな豆腐製品が作られていくというステップとなります。
なお、使用する大豆は作りたい製品により実は使い分けられています。各製品の種類に合った豆乳が大豆から作られ、加工されていくのです。
木綿豆腐

温かい豆乳に凝固剤(にがりなど)を加えて凝固させたものを崩し、豆腐の形を作る型箱に入れます。
これに重しを乗せて押すのですが、木綿豆腐用の型箱には穴が空いていて水分や油分が抜けるため、しっかりとした食感の木綿豆腐ができあがるというわけです。
生活者に販売される際はこれを水に晒し、一丁の大きさに切り出したものを包装しています。
なお木綿豆腐の名前の由来は、型箱に引いた木綿の布の布目が豆腐の表面に付いていたことから木綿豆腐と呼ばれるようになりました。
絹ごし豆腐

なめらかな食感が特徴の絹ごし豆腐は豆乳のまま型箱に入れて、その中で凝固させて形作ります。一度凝固させてから型箱に入れる木綿豆腐とは製法が異なるのです。
そのため、絹ごし豆腐の型箱には穴のないものを使います。型箱に入れて水分を取るという工程がない分、豆乳の味が濃くないと豆腐自体の味もぼやけてしまうため、豆乳は木綿豆腐で使うものより濃度の濃いものを使って作られます。
絹の布でこしたようになめらかな口あたりで、キメの細かい見た目をしていることから絹ごし豆腐と呼ばれていますが、絹の布を使用しているわけではありません。
栄養価は違うの?
エネルギー量を100gあたりで比べると、木綿豆腐は72kcal、絹ごし豆腐は56kcalと木綿豆腐が少し高め。その他の栄養素でも、たんぱく質・脂質などでは木綿豆腐の方が絹ごし豆腐より少し高めの値を示します。
これは木綿豆腐が重しで圧搾して水分を取り出すため。この作り方の違いから、同じ重量あたりの栄養素の割合も異なるというわけです。
少しの差ではありますが、「少量しか食べられないので、より効率よくたんぱく質をとりたい」などの場合には、木綿豆腐を選んでみるのがいいでしょう。
なお栄養価のうちカルシウムやマグネシウムなどのミネラルは、使用される凝固剤の種類にも影響を受けます。
期待する栄養価のほか、料理や食感の好みによっても使い分けよう
元は同じ大豆から作られる木綿豆腐と絹ごし豆腐。製法の違いによって、できあがる豆腐が大きく変わることをお分かりいただけたでしょうか?
豆腐は冷奴のように生で食べる他、炒めたり焼いたり、揚げたり煮たり……と調理の幅が大きい食材。豆腐ステーキなどのように水分を出したくない料理には木綿豆腐を使ったり、やわらかい食感を好む場合は絹ごし豆腐を使ったりと、料理の内容や好みによって使い分けてみてくださいね。