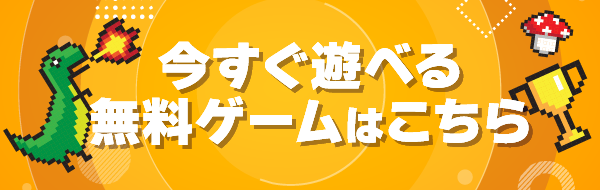アメリカのブルックヘブン国立研究所(BNL)で行われた研究により、陽子内部に強い量子もつれが存在していることが示されました。
陽子は周期表に存在するあらゆる原子核の内部に存在しています。
新たな研究ではこの陽子内部の量子もつれの存在は、内部のクォークやグルーオンを束ね、その一体化を促進する役割を担っている可能性が示されました。
この結果は、量子もつれの存在がわたしたちの物質世界そのものを根底から支えていることを示しています。
研究内容の詳細は『Reports on Progress in Physics』にて発表されました。
目次
- 量子もつれは単なる不思議な現象ではない
- 量子もつれは私たちを作る物質を支えている
量子もつれは単なる不思議な現象ではない

陽子といえば「3つのクォーク」でできていると教科書的には言われます。
しかし実際は、グルーオンや海クォークが絶えず生まれ消えている、ひどく賑やかな量子世界が詰まっています。
これらは強い力(色荷相互作用)によって互いにぎゅっと結びつき、単独で外へ“飛び出す”ことができません。
こうした「閉じ込め」の仕組みを理論的に見るとき、単に「力が強いから抜け出せない」のではなく、粒子同士が量子もつれによって不可分な波動関数を共有しているという見方がより自然ではないか――というのが、近年注目されている考え方です。
しかし、これまでの研究では高エネルギー散乱実験のデータだけでは、衝突前に陽子内部でどのような量子的絡み合いが起きているかを直接見ることは難しく、さらに多数の粒子が同時にもつれ合う複雑な状態をどう評価するかという理論的課題もありました。
しかし最近では、量子情報科学の発展により、たくさんの粒子同士のもつれ具合を数値で測る(エンタングルメントエントロピー)技術が整ってきました。
さらに、衝突実験の精度や規模も大きく向上したため、それまで難しかった「陽子の中のもつれ」を実際の実験データから確かめられるようになってきたのです。
そこで今回、国際的な研究チームは、陽子内部のクォークやグルーオンといった素粒子たちがどれくらい深く量子的に絡み合っているかを新しい視点で探ることにしました。
量子もつれは私たちを作る物質を支えている

陽子内部で粒子はどのように絡み合っているのか?
答えを得るため研究者たちは「電子を探り針として陽子にぶつける」高エネルギー散乱実験を行いました。
具体的には、加速器で非常に速く加速した電子を、陽子(標的)に向けて衝突させます。
電子は電荷を持ち、電磁相互作用を通じてクォークとやり取りをするため、陽子の内部構造を“こまかく”探るプローブ(探り針)として最適です。
電子自身はクォークやグルーオンよりも“シンプル”な構造なので、衝突後の分析が比較的わかりやすいという利点もあります。
衝突が起きると、陽子の内部に潜んでいたクォークやグルーオンとの相互作用が発生し、その結果、たくさんのハドロン(新たに生成される中間子やバリオンといった粒子)が飛び出してくるわけです。
研究では、衝突後に飛び出すハドロンの数やどの方向にどのくらいのエネルギーをもって飛び出すかといった「分布パターン」を詳しく測定しました。
粒子検出器は衝突点の周囲を取り囲むように配置されていて、飛んできた粒子の軌跡やエネルギーを高精度で記録します。
これにより、陽子内部にあったクォークやグルーオンがどのくらい“絡み合って”いたかを理論モデルを用いて推定します。
衝突前のクォークやグルーオンの状態を直接見ることはできませんが、それらが「どのようにもつれていたか」という情報が、衝突によるハドロン生成の仕方や分布の“乱雑さ”に反映される、という理論的な予想が近年提唱されています。
もし“もつれ”が弱ければ、衝突後の分布は比較的バラバラになりますが、強いもつれ状態であれば、「飛び散り方の乱雑さ」や「粒子生成数」のパターンが理論計算とピタリ一致する、というわけです。
(※この予測には、量子情報理論でいう「エンタングルメントエントロピー」などの指標が用いられました)
すると、クォークやグルーオンがほぼ最大限にもつれた状態を仮定すると、陽子から飛び出すハドロンの観測データとすんなり符合する――これは、「陽子は単にクォーク3つの寄せ集め」ではなく、「大量の成分が不可分に結びついた一つの量子システム」だという見方を裏付ける大きな発見です。
たとえるなら、たくさんのダンサーが思い思いにステップを踏むのではなく、最初から全員が一体化した振り付けを知っていて、それを息ぴったりに踊っている――そんなイメージに近いでしょう。
もし互いがもつれていなければ、一部だけが飛び出す、あるいはまるで分解してしまうなど、陽子という安定した粒子としての姿は維持できないのかもしれません。
クォークやグルーオンもまた、全体が量子もつれによって統合されているからこそ、陽子という安定した姿を保てるわけです。
そして、この“チーム全体”の動きによって、私たちの体を含む物質が安定して存在できるということは、量子もつれが日常世界の基盤をなしている可能性を強く示唆します。
というのも、私たちの身体や周囲の物質は無数の陽子・中性子によって作られているからです。
つまり、陽子の内部にもつれがなければ、そもそも私たちを構成している物質は今のように安定して存在できない可能性が高いのです。
もつれは特殊で不可解な実験結果ではなく、“物質があるという現象”そのものを支えているわけです。
「量子もつれ」というとSF的なイメージや特殊な実験を想起しがちですが、私たち自身を含むあらゆる物質にも「もつれ」が当たり前のように組み込まれているのです。
今回明らかになった「陽子内部の量子もつれ」を数値的に捉える手法がさらに成熟すれば、核子や原子核、さらには物質のあらゆる安定性をより精密に理解できるようになるでしょう。
今後建設予定の電子イオン衝突型加速器(EIC)などでは、さらに大きな系での核子同士のもつれも探究できるため、高エネルギー物理や核物理学の基盤自体が“もつれ”を中心に再定義される可能性すらあります。
そうなれば、物質観のみならず、量子情報理論や次世代の実験技術にも波及し、私たちの科学の見取り図を大きく変えていくことでしょう。
元論文
QCD evolution of entanglement entropy
http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/ad910b
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部