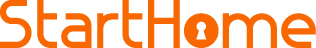内燃機関超基礎講座 | 可変バルブタイミング機構 バルブのタイミングを可変とする現代エンジンの必須装備

可変バルブタイミング機構(Variable Valve Timing)は、カムフェーザー(Cam Phaser)とも呼ばれる現在のエンジンにはもはや必須の仕掛けである。原理はシンプルだが、正確に緻密に制御するのは簡単ではない。
可変バルブタイミング機構、VVT(Variable Valve Timing)はカムフェーザーは別名。クランクシャフト、あるいはカムスプロケット(もしくはプーリー)に対するカムシャフトの位相角(phase:フェーズ)を変化させることで、カムシャフトがバルブに働きかける(バルブを押し下げる)タイミング、すなわちバルブタイミングを変更するというもの。

その原理はカムスプロケット部に取りつけられるカムシャフトの角度を回転させるように動かすという、ある意味単純なものだが、その“絵に描いた餅” のように単純な機構を確実かつ正確に動かすためには、高度な技術が必要不可欠だ。しかも高トルクが必要とされるカムシャフトの制御には、高出力のアクチュエーターが求められるわけだが、エンジン内部で現実的に利用可能な動力源というと、最近まで油圧以外に選択の余地はほぼないに等しい状態だった。
詳しくは後述するが、その傾向は電動式VVTが普及しつつある現在においても同様で、コスト面まで含めて考えると、油圧ベーン(ベーン=風車)式と呼ばれる、油圧式VVTが主流とならざるを得ない状況だ。
こういうと油圧ベーン式がまるでローテクなようだが、油圧ベーン式が世の中に初めて登場した当初は実用性が疑問視されるほどに難しい技術とされていたという経緯がある。電動式VVTがなかなか乗り越えることのできない、油圧ベーン式のメリットは、あらゆる課題を乗り越えながら、長年に渡って鍛えられてきたという歴史から生まれたものであり、一見シンプルなその構造には、加工精度を含め数多くの工夫が凝らされている。
とはいえ、現在の制御が電気による制御信号を用いて行なわれる以上、制御信号の先に油圧機構というワンクッションを持つよりは、制御信号で(ほぼ)ダイレクトに駆動が可能な電気式の方が理想的であることもまた事実。しかし、そこにもやはり理由がある。
要は回転運動を行なうアクチュエーターといえばモーターなのだが、カムスプロケット部分に収まる大きさ(体格)で、前述のようなカムシャフトを回転させるための高トルクを生み出すためには、モーター単体では不可能であり、高倍率のトルク増幅が必要だったのだ。それもカムスプロケット部に収まるという寸法的制約の中でだ。
ちなみに、下の写真(とトップの写真)で紹介しているトヨタのVVT-iEと呼ばれる電動式VVTでは、サイクロイド減速機構という一段で大減速が可能で、なおかつ精密な位置決めという制御に必要な、ゼロバックラッシュ(つまりガタがない)という要素を持つ特殊な機構が使われている。もちろん、そのメリットは絶大で、可変幅、応答性は油圧ベーン式を大きく上回り、そして角度を自在に操れるなど制御の自由度も格段に高まるのだが、それを制御するECUにも高い能力が必要となり、実装されるソフトウェアの高度化(当然開発工数も増加)が求められるということも忘れてはならない。